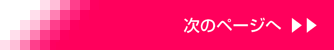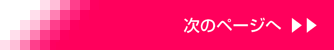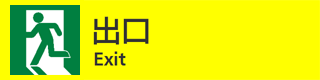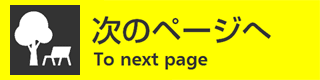|
 |
■大場川
大場川は、利根川水系中川の支流で、1676年に埼玉県吉川市付
近の干拓の際に、排水のため開削された。吉川市内から三郷市内を
南へ流れ、都県境では、都立水元公園へ水を流す。その後、中川へ
合流する。本来は北側が上流で南側が下流であるが、高低差があま
り無いためか、また沿岸に排水機場が多く排水の関係か、川が逆流
している事が多々ある。画像中央の浮遊物は、画像手前(下流側)
から上流側に流れていったものである。
|
 |
■上第二大場川
上第二大場川は、埼玉県吉川市のJR武蔵野線吉川美南駅付近から
付近の用水路や吉川美南調整池などの水を集め、三郷排水機場まで
を流れる河川。元々は大場川と共に東京都葛飾区まで流れていたが
三郷放水路建設の際に、大場川と共に分断された。しかし伏越で繋
がれた大場川に対し、第二大場川は完全に分断され、現在は上流側
と下流側で別河川となる。三郷放水路建設の際に、流路を東方向へ
と曲げられ、大場川と交差した先で三郷排水機場へ注ぐ流路となる
が、普段は水門で閉ざされる。
※矢印を画像にかざすと上第二大場川の三郷排水機場側の画像へ。
|
 |
■大場川と上第二大場川の交差部
大場川と上第二大場川は、大場川橋(画像右・大場川)および新大
膳橋(画像中央・上第二大場川)付近で交差する。また、この交差
部の南側には三郷放水路があり、大場川水門で仕切られている。さ
らに隣接して大場川伏越が設置される。河川の交差、水門、伏越が
一度に見られる場所である。 |
 |
■大場川水門
大場川および上第二大場川は、三郷放水路によって分断されている
が、厳密には大場川水門にて三郷放水路と合流する事は可能である。
ただし非常時以外は閉鎖されている。
※矢印を画像にかざすと、三郷放水路側から見た画像へ。
|
 |
■大場川伏越(上流側)
大場川水門に隣接して小振りな水門が2基設置されているが、これ
が大場川伏越である。取水部には格子が取り付けられているが、こ
れは浮遊物を吸い込まないようにするため。伏越は河川の上流と下
流を導水管で結んでいるが、この導水管に浮遊物が進入すると管を
塞いでしまい、事故につながるためである。ただし訪問時には先述
のように川が逆流していたため、取水部から水が湧き出ていた。
|
 |
■三郷放水路
中川・江戸川流域は低層地帯であるため、洪水多発地帯となってお
り、加えて中川の水質汚濁が深刻となっていたため、1973年に
三郷放水路が建設された。三郷放水路は全長1.5kmで、西側の
中川との合流部には三郷水門が、東側の江戸川との合流部には三郷
排水機場が設置される。この放水路の下を、大場川の導水管が通る。
※矢印を画像にかざすと三郷排水機場の画像へ。
|
 |
■大場川伏越(下流側)
三郷放水路を潜った大場川は、その先で再び地上へと顔を出す。下
流側は上流側ほど複雑な構造になっていないが、突然現れる川が伏
越を象徴してる。
|
 |
■大場川伏越(下流側・近景)
上記の画像を、別アングルから見る。吐水部の水門の形状から、こ
ちらは下流側であるはずだが、先述のように訪問時には川が逆流し
ていたため、浮遊物進入防止用の浮き輪が逆方向に湾曲している。
|
 |
■大場川伏越(下流側・遠景)
伏越を遠景で見る。大場川の護岸にはマツバギクが植えられ、緑化
だけでなく初夏には花を咲かせるなど、目を楽しませる。大場川は
この先、東京都葛飾区で都立水元公園に注ぎ、新大場川水門で中川
に合流する。大場川伏越は1973年に三郷放水路が建設された際
に、大場川が分断されるために設置された。大場川と三郷放水路を
平面交差させた際、緊急時に、水害対策として建設されたはずの三
郷放水路の水が大場川に流入し氾濫してしまうため、非常時以外は
分断し、伏越という手段で立体交差する方法を取った。
|