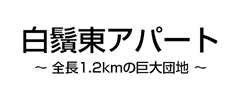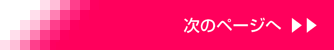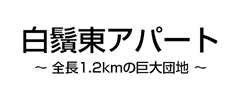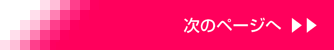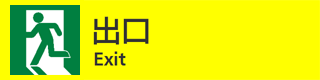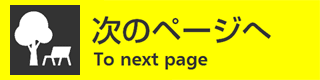|
 |
■白鬚東アパート
白鬚東アパートは、地盤が軟弱で木造家屋と工場が密集混在してい
る「江東デルタ地帯」の最北端にあり、大震災災害から住民を守る
ために防災6拠点の一つとして、東京都が「白鬚東地区防災拠点」
という名称で建設が計画された。1972に建設が始まり、14年
かけて完成された。全18棟からなる団地であるが、最南端から最
北端までは1.2kmもの長さとなる。しかも建物は全棟が繋がっ
ている。これは大火災時に建物自体が防火壁となり、延焼を防ぐた
めである。
|
 |
■シャッターを備えたベランダ
白鬚東アパートは、市街地で大火災が発生した際、熱風や火の粉か
ら住宅の開口部を防御するため、墨堤通り側バルコニー部分に防火
シャッターを備える。シャッターの材質は大火の高温に耐えうる強
度を持つ。また火災時はシャッター面が熱くなるのを防ぐため、屋
上にドレンチャー用水槽を備え、シャッターに放水する。タンク容
量は合計で1005tとなる。
※矢印を画像にかざすとドレンチャー用水槽の画像へ。
|
 |
■東白鬚公園
白鬚東アパートと隅田川に挟まれた場所に広がる公園。10ヘクタ
ールもの広さがあり、野球場・学校・テニスコートが設置される。
この公園は、災害時には約10万人が収容できる避難場所となる。
避難広場として機能するため、樹木の植樹や、池の造成などで避難
者を火災の炎や熱風から守る工夫がされている。
|
 |
■公園散水用の放水銃
東白鬚公園に避難した人々を、火災時の熱風や火の粉から守るため
白鬚東アパートには、散水用の放水銃が等間隔に設置されている。
|
 |
■ブリッジシャッター
白鬚東アパートの12号棟〜15号棟は住居棟ではなく、特に13
号棟と14号棟は防災備蓄庫となる。窓の一切ないコンクリートの
建物は異様そのものである。13号棟と14号棟の間は都道461
号線支線が通る。都道の上部には鋼製の渡り廊下が見えるが、この
部分も災害時には鋼製シャッターで遮断され、防火壁となる。渡り
廊下状のシャッターであることからブリッジシャッターと呼ばれる。
都道の先には首都高速6号線の堤通インターや、水神大橋を介して
南千住方面へと抜けられるため、車の往来が多い。
|
 |
■隅田川神社の鳥居
白鬚東アパートの6号棟と7号棟の間には、鳥居が鎮座する。この
鳥居は隅田川神社のものである。隅田川神社は、創建時期は不詳で
あるが、源頼朝による創建と伝えられている。元々は浮島神社の名
前で、地元では「水神様」の名で親しまれた。隅田川一帯の守り神
であり、水運業者や船宿などで働く人たち、また「水神」の名から
水商売の人々にも信仰された。神社の参道に当たる部分は、防災団
地において数少ない開口部分であるが、災害時にはシャッターで閉
ざされる。
※矢印を画像にかざすとシャッターの画像へ。
|
 |
■榎本武揚像
9号棟付近にある梅若公園には、幕末に活躍した武士であり政治家
であった榎本武揚の銅像が建立される。榎本武揚は1836年に誕
生し、1862年にオランダ留学、1868年には海軍副総裁とな
る。函館戦争の後、北海道開拓に従事するなど、幕末の日本を生き
抜いた人物である。晩年は向島に住居を構えた事から、銅像がこの
地に建てられた。
|
 |
■白鬚東アパートを眺める
白鬚東アパート建設の背景には、戦火を免れた木造住宅が密集する
向島地区の防災対策があった。大地震発生時に予想される市街地火
災から避難場所を防ぐため、防火壁の役割を持つ大規模建造物が建
築された。防火シャッターや散水用放水銃は、幸いにも現在に至る
まで活躍したことはない。
|