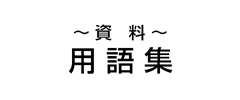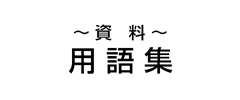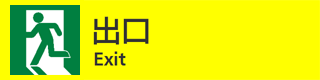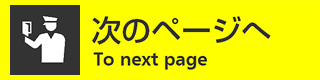| 吊り掛け駆動 |
吊り掛け駆動とは、モーターを車輪軸と台車枠に橋渡しにする様に
設置し、モーターから直接、車軸ギアに動力を伝え駆動させる方式
である。構造が非常に単純なため19世紀末から長期に渡り多くの
電車に用いられたが、モーターの重量が大きく台車に負荷を与える
事と、高速運転に不向きな事、何より振動と騒音が激しい事が欠点
である。そのため、1951年頃から各社は、高速運転と静音性に
優れた「カルダン駆動」を採用し、吊り掛け駆動は、過去の技術と
なった。路面電車では現存する車両も多いが、関東の大手私鉄では
東武鉄道5000系が最後の車両であった。日本全国の大手私鉄で
も名古屋鉄道と西日本鉄道でわずかに残るのみ。ただしJRの電気
機関車では、単純な構造と信頼性から、新造車両でも現在までこの
方式を採用している。
|
| カルダン駆動 |
高速運転に不向きであった吊り掛け駆動は、モーター重量の半分が
車軸にかかる構造で、よって車輪からの振動も受けやすい。これを
改善すべく、モーターを台車枠に固定し、車軸との間に継手を介す
ことによって駆動させる方式が発明された。これがカルダン駆動で
ある。この方式によってモーターが振動を受けにくくなりモーター
の小型化、高速化が実現し、そして故障も激減した。1951年頃
から普及し現在では一部の電気機関車を除いて標準の仕様となる。
当初はモーターをレール方向に配す直角カルダン方式が主流であっ
たが、台車の小型化の流れに支障となる事から、現在ではモーター
を枕木方向に配す並行カルダン方式が主流である。
|
| 純電気停止ブレーキ |
走行中の車両を停止させるには車輪を制輪子(ブレーキシュー)で
押さえつけ、その力で停止させる方法が一般的。自転車のブレーキ
が代表的な構造である。しかしスムーズな停止に難があり、何より
ブレーキシューの磨耗が激しく、莫大な維持費がかかる。そのため
減速時には電気ブレーキ(モーターが発電機の様に電気を起こして
その抵抗力で車両を減速させる)を使い、完全に停止させる時のみ
ブレーキシューで押さえつける方法が、現在の鉄道車両では主流。
そして完全停止時にも電気の力を使用する新しいブレーキが純電気
停止ブレーキである。減速時は従来どおりであるが、完全停止時に
は、モーターを逆回転させて停止させる。今後の車両にはこの方式
が採用されるものと思われるが、緊急時の急ブレーキのこともあり
全ての車両はブレーキシューも残されている。
|
| A−Train |
家電や、通信機器などの製造メーカーである日立製作所は鉄道車両
製造などの重工業も手がける。特に新幹線車両の車体製造は日立の
比率が多く先頭車両に至っては、ほぼ独占状態となっている。また
「A−Train」と呼ばれるアルミ車両製造の技術は車体強度の
向上とコスト削減を両立し、かつ溶接箇所が目立たなく見た目にも
美しい鋼体の仕上がりとなっている。この技術を採用した鉄道車両
は近年多く、下記にその車両を掲載する。
| 西武鉄道 |
20000系、30000系 |
| 東京地下鉄 |
05系(一部)、10000系
15000系、16000系 |
| 東武鉄道 |
50000系列 |
| 首都圏新都市鉄道 |
全形式 |
| 東葉高速鉄道 |
2000系 |
| 阪急電鉄 |
9000系、9300系 |
|