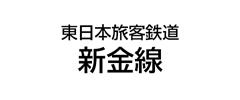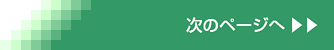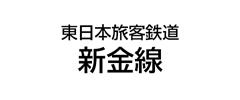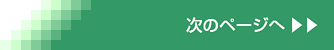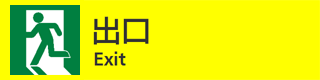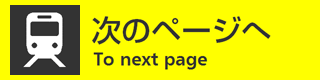|
 |
■新小岩信号場駅
新金線の起点は小岩駅となるが、小岩駅から新小岩信号場駅までは
総武本線と並走する。そしてこの新小岩信号場駅で進行方向を変え
金町方面へと向かう。新小岩信号場駅は元々、貨物駅として開業し
一旦は操車場へと格下げされたが現在は再び貨物駅となっている。
ただし実際に荷受はされておらず、金町方面への貨物列車の方向転
換や、非電化区間である越中島支線へ向かう列車の機関車交換場所
として使用されている。 |
 |
■総武本線との分離部
新金線は小岩へと向かう総武本線としばらく並走するが、環七通り
をくぐる辺りで本線と分離し、北向きに進路を変える。つまり新金
線の営業キロは新小岩信号場駅からここまでが重複している。画像
の下側が新金線。 |
 |
■北向きに進路を変える新金線
上の写真を、金町方面向きに撮影。線路はこの先、地平から盛土高
架となり、蔵前橋通りを越える。新金線は全線単線であるが、高架
部を含め、ほぼ全線にわたり複線分の用地が確保されている。なお
この付近は葛飾区と江戸川区との区界であり、新小岩信号場駅から
葛飾区東新小岩、江戸川区上一色、葛飾区奥戸、江戸川区上一色と
細かく住所が変わる。 |
 |
■中川放水路橋梁
蔵前橋通りを越えた線路は、そのまま高架で新中川に差しかかる。
画像は中川放水路橋梁。橋梁の名称と河川の名称が異なっているの
は橋梁完成後の1965年に中川放水路が一級河川に指定され、新
中川へと名称変更されたため。なお新中川自体1949年掘削開始
の新しい河川であり、橋梁も路線開業のはるか後、近隣が掘削開始
となった1959年に完成している。 |
 |
■地平部を進む
新中川を渡り終えた線路は左へとカーブしながら盛土高架から地平
へと降りる(画像は逆方向を撮影。手前が金町側)住所も江戸川区
西小岩、葛飾区細田と再び区界を縫うように進む。 |
 |
■架線柱に貼付された注意書き
地平を進むため、架線柱も子供の目に付きやすい位置の設置となる
が当然ながら線路内は立入禁止である。しかし架線には1500V
の電流が流れているため万が一の事態があれば非常に危険である。
そのため柱には注意書きが貼付されている。しかし何故か路線とは
全く縁のない新幹線車両が描かれている。 |
 |
■東京街道踏切付近
新中川を渡り終えてひたすら直線部を進んできた線路は、東京街道
踏切付近で進路を右に変える。画像下には河川を越えるガーター橋
が見えるが、実際には川は暗渠化され植物が植えられている。この
先、住所は葛飾区高砂となり、はるか遠くには、斜張橋である高砂
橋の鉄塔や(画像中央右寄り)京成線の鉄橋が見える。 |
 |
■京成線を潜る
高砂橋(新金線部分のみ富士見橋)を潜るとその先には京成線の線
路が登場する。画像右側に進むと京成高砂駅がある。 |
 |
■暗渠部をガーター橋で越える
江戸時代には農村として栄えた葛飾区は農業用水が多く敷かれたが
農業の衰退によって、多くは暗渠化された。そのため、新金線には
水のない川跡をガーター橋で渡る箇所が多く、先述の東京街道踏切
以外にも高砂踏切付近や(左画像)三重田街道踏切付近でも(路線
概要画像)ガーター橋が存在する。なお暗渠化された河川は一部が
道路拡張用地として使われ、整備された道路は、歩道も併設された
安全な道路となる。 |
 |
■新宿新道踏切
新金線は葛飾区新宿(にいじゅく)で水戸街道と交差し、この部分
に広大な踏切が存在する。新金線自体、本数の少ない路線ではある
が、国道との交差部ゆえ一たび遮断機が下りると大渋滞となる。そ
のため踏切の前後には信号を設け、通常時は踏切手前で一時停止す
る事なく自動車が通過できるようになっており、渋滞発生を抑止し
ている。 |
 |
■第二新宿踏切
第二新宿踏切を越えると線路は右へカーブしその先の常磐線の線路
を潜る(画像中央奥が常磐線線路)しばらく常磐線と並走した後に
金町駅に到着する。新金線の金町駅はJR貨物の管轄でありホーム
等はない。かつて当駅より三菱製紙への専用線が敷設されていたが
現在は撤去されている。なお新金線は、地元住民や葛飾区から旅客
化が要望されている。水戸街道との交差部の問題や採算性から難題
は多いが、実現されれば利便性は向上する。 |