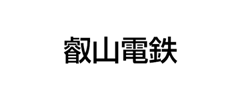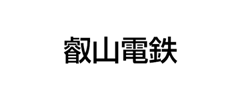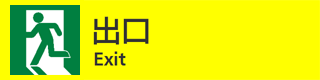|
 |
■デオ730形「ひえい」(2018年)
比叡山・琵琶湖の周遊観光ルートの活性化の一環として導入された車両。700系732号を改造し、神秘的なイメージをコンセプトとした楕円をモチーフとした内外装とした。車体は深緑色に塗装され、比叡山の山霧をイメージした金色のストライプが窓下に入れられた。鉄道友の会「ローレル賞」またグッドデザイン賞も受賞している。
|
 |
■デオ900系(1997年)
叡山電鉄の代表車両で「きらら号」の愛称を持つ。京都市営地下鉄の国際会館駅延伸に伴い、延伸区間と競合する叡山電鉄を「観光路線」としてアピールするために登場した車両。鞍馬の紅葉が楽しめるよう側面窓は天井付近まで拡大、車内からの眺望を向上させた。画像の第1編成は紅色に、第2編成は朱色に塗られている。鉄道友の会「ローレル賞」受賞車両。
|
 |
■デオ800系(1989年)
京阪電車の出町柳駅延伸に伴い、輸送力増強を目的として登場した車両。従来の叡山電車は1両の車両を2両連結していたが、この形式からは2両固定編成となり、定員は2割増となった。2編成が在籍、叡山電車の主力として活躍する。 |
 |
■デオ810形(1993年)
デオ800系は1993年製造車両から仕様が若干変更された。モーター制御方式の変更により床下機器に余裕が無いため一部の機器を屋根上に取り付けた。そのため屋根上スペース確保の関係でパンタグラフ形状が小型化されている。制御方法の違いから810形とも呼ばれる。画像の815編成は沿線の四季のイラストが描かれた「ギャラリートレイン・こもれび」号。
|
 |
■デオ700系(1987年)
叡山電車初のワンマン運転対応車両。また初の冷房搭載車両である。ワンマン運転車両を印象付けるため、従来は経営母体であった京福電気鉄道京都支社(嵐電)と同様のグリーン系の塗色であった叡山電車において、京福福井支社車両と同様のマルーンとベージュの新塗色となった。ただし現在はアイボリー地に、沿線をイメージしたストライプの入る新塗装へと変更された。
|
 |
■デオ700系リニューアル車(2019年)
1987年に登場したデオ700系は、登場から30年が経過した2019年よりリニューアル工事が施工された。車椅子スペース設置などバリアフリー化や車内照明のLED化、車体前面強化やデザインの変更が行われている。改造第一号である722号は、沿線神社仏閣をイメージした朱色に塗装され、3月21日に営業運転を開始した。
|