 |
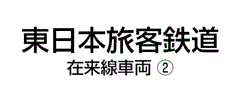 |
 |
 |
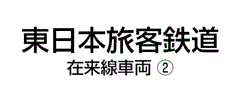 |
 |
| にょほほ電鉄−車両−東日本旅客鉄道(在来線車両2) |
||
 |
|
|
| 駅名標 東日本旅客鉄道 |
||
 |
|
|
 |
|
|
 |
■E235系(2015年) 池袋、新宿、渋谷など東京を代表する街を結ぶ環状線である山手線の車両。E231系500番台を置き換えるために登場した。利用客サービス向上だけでなく、エネルギーコスト低減やメンテナンス低減を実現。鋼体はレーザー溶接を適用し水密性を確保した。また車内は一部を除いて紙広告を廃止し電子化されている。 |
 |
■E231系500番台(山手線:2002年〜2020年) 205系の置き換え目的として登場した車両。常磐線快速や総武線各停等に導入されている0番台の機能に加え、乗降扉鴨居部に液晶画面を2つ装備し、首都圏の運行情報や次駅表示広告などが表示される。また前面形状はオリジナルとなる。2015年よりE235系が投入されたため、現在は総武線へ転属されている。 |
 |
■205系(山手線:1985年〜2005年) 当初、次世代車両として中央線に投入された201系は製造コストが高価であり、コストダウンを目的として開発された。軽量ステンレス車体や電気指令式ブレーキは国鉄初の採用となる。山手線の車両をE231系に置き換える計画と並行し、他線区に残る103系置換えのため改造のうえ転属、また一部車両は富士急行に譲渡された。 |
 |
■103系(山手線:1963年〜1988年) 高度経済成長期にはラッシュ対策として大量の車両新造が急務となったが、当時国鉄が製造した101系では製造コストが高価なため新たに電動車の比率を下げた、製造費用の安い車両を作った。この車両が103系である。103系もまた最初の投入線区は山手線となる。山手線からは1988年に撤退した。 |
 |
■E233系1000番台(2007年) 埼玉県の大宮から東京駅を経由し神奈川県の横浜に至る京浜東北線と、そこから桜木町や磯子を経由し大船に至る根岸線に使用される車両。209系の置き換えに伴い投入された。中央線快速に投入された0番台との相違点は、寒冷地を走行しないためドアスイッチが省略されている。前面下部にはホーム検知装置が設置されているため、やや窪んでいる箇所がある。 |
 |
■209系(京浜東北線:1993年〜2010年) 国鉄より引き継いだ103系の置換えのため登場した車両。鉄道車両の税法上の減価償却期間である13年で廃車としても問題ないコストとする事で、新技術の積極的な採用が行える事を目的とした。廃車後のリサイクル計画の策定など、環境に対する配慮もされたが「価格半分・車重半分・寿命半分」のコンセプトが誤解され「走ルンです」と揶揄されているのが気の毒。 |
 |
■E233系7000番台(2013年) 東北新幹線建設の地元自治体への見返りとして開業し、埼玉県の大宮から武蔵浦和、戸田、赤羽線区間、山手貨物線を経由し大崎駅に至る、埼京線の車両。205系の老朽化に伴い登場した。京葉線用5000番台の機能に加え、車内照明にはLEDを採用し消費電力を40%削減。また痴漢対策から1号車に防犯カメラを4台設置する。埼京線、川越線で活躍。 |
 |
■205系(埼京線:1989年〜2016年) 元々は、東北新幹線建設による騒音を懸念し反対運動を起こした自治体への見返りとして計画された埼京線であるが、いざ開業すると新幹線の走行音よりも、当時使用されていた103系の走行音の方が大きく、沿線住民から苦情が来る事態となった。そのため205系を投入する事となり、わずか1年半で103系を置き換えている。老朽化に伴い2016年に撤退した。 |
 |
■E257系500番台(2004年) 中央本線特急に導入されたE257系は房総特急や総武本線特急にも導入され、旧型特急車を置換えた。先頭車は正面に貫通扉を設け基本番台とは印象が異なる。また、255系とイメージを合わせたホワイト地にイエローとブルーの塗色となっている。 |
 |
■E233系5000番台(2010年) 東京駅から、東京ディズニーリゾートや千葉の湾岸沿いを経由して千葉県の蘇我に至る京葉線の車両。205系や201系の老朽化に伴い登場した。京浜東北線用1000番台の機能に加え、高速無線通信「WiMAX」を利用したディスプレイでの映像配信が可能となっている。また外房線・内房線などへの乗入れの関係から6両+4両の分割編成も存在する。 |
 |
■209系500番台(京葉線:2008年) 総武線各駅停車に投入されていた209系500番台は、その後に京浜東北線に転属された編成を、京葉線201系の置き換え目的でさらに京葉線に転属された。4編成が活躍したが、現在はうち3編成が武蔵野線に再転属され、1本のみの存在となる。 |
 |
■255系(1993年) 房総特急の旧型車両を置き換えるために製造された車両。海岸を走る列車であることから、床材は滑りにくい材質を採用する。塗色はホワイト地に房総の海と菜の花をイメージしたブルーとイエロー。なおJR東日本の特急車では初めてVVVFインバータ制御を採用した。「グッドデザイン賞」受賞車両。現在は房総特急運用から撤退、臨時列車に使用される。 |
 |
■E331系(2007年〜2014年) E231系をベースとし、JR通勤車では初めて、台車が連結器を兼ねる連接車となる車両。車体長は1両当たり14mと短く、そのため通常の車両と同じ長さながら14両編成となる。また車輪の車軸そのものをモーター回転軸とした、ダイレクトドライブモーターを採用。1編成のみの存在。故障頻発のため2014年をもって引退した。 |
 |
■205系(京葉線・新製編成:1990年〜2011年) 1990年に全線開業した京葉線は増備車両として205系が投入されたが、京葉線投入編成は前面デザインが大幅に変更された。沿線にある東京ディズニーリゾートをイメージしてデザインされた前面形状は、前頭部全体を白いFRPで覆われた構造となりストライプも濃いピンク色となった。海沿いを走る路線ゆえ車体の劣化が早く、京葉線からは2011年に撤退した。 |
 |
■205系(京葉線・転属編成:2002年〜2011年) 103系の老朽化に伴う置き換え用として、山手線や総武線から転属された編成は、従来通りの前面形状のままとなる。新製編成と共に2011年をもって営業運転を終了している。 |
 |
■201系(京葉線:2000年〜2011年) 国鉄初の電機子チョッパ制御を採用した201系は、103系の置き換えを目的として総武線用車両を転属させた。最初に投入された7編成は6両+4両の組成となるため、外房線や東金線への乗り入れ運用にも使用された。JR東日本管内では、最後まで201系が残った線区であったが、2011年をもって引退した。 |
 |
■103系(京葉線:1986年〜2005年) 京葉線の開業時から活躍した車両。開業に際して京浜東北線や横浜線から転属され、当初は朝ラッシュ時10両編成、日中は6両編成で運用されていた。205系の転入に伴い、京葉線からは2005年に撤退した。 |
 |
■E231系0番台(武蔵野線:2019年) 東京の府中本町から、埼玉県の新座や南浦和、千葉県の新松戸を経由し西船橋に至る武蔵野線は、当初は山手貨物線のバイパスとして計画された貨物専用線であったが、旅客線に転用した経緯がある。従来使用の205系の老朽化のため、山手線用E231系の総武線への転用に伴い余剰となった総武線E231系を、武蔵野線へ玉突き転用し、205系を置き換えている。 |
 |
■209系500番台(武蔵野線:2010年) 205系の老朽化のため、京葉線へのE233系投入に伴い余剰となった209系500番台を8両編成化のうえ転入した。2018年には総武線からの余剰車も転入し、205系を置き換えている。 |
 |
■205系(武蔵野線・新製編成:1991年〜2019年) 京葉線東京駅開業に伴い、直通運転を行う武蔵野線の運用拡大のため投入された車両。前面形状は京葉線のものと同じく専用デザインとなるが、京葉線車両のホワイトとは異なり、シルバーに塗装されている。E231系の転入に伴い2019年をもって廃車となった。 |
 |
■205系(武蔵野線・転属編成:2002年〜2020年) 103系の置き換えのため、山手線から205系を転属する事となったが、山手線205系の転属先は複数路線にわたり、転属先の路線は短編成が多く電動車が足りなくなる。そこで武蔵野線転属車両は、少ない電動車数でも同じ性能が確保できるよう、VVVFインバータ化改造が行われた。この改造電動車は5000番台を名乗る。老朽化に伴い2020年に引退した。 |
 |
■E233系8000番台(2014年) 南武線は、東京の立川から多摩地域を南北に結び、神奈川県の川崎に至る本線と、尻手駅から浜川崎駅に至る支線で形成される路線で元々は多摩川の砂利を輸送する南武鉄道を起源とする。南武線205系の老朽化に伴い投入されたのが8000番台である。ストライプにはラインカラーのほか、先頭車側面には沿線の建物のシルエットがアクセントとして加えられた。 |
 |
■E127系(1995年新製 → 2024年南武支線転入) 新潟支社管内で使用された115系の老朽化に伴い登場した車両。車体は209系をベースに、地域性を考慮し115系と同様の3扉とした。12編成が製造されたが、10編成が「えちごトキめき鉄道」へ譲渡。残る2編成も弥彦線の車両統一のため余剰となるが、すると今度は南武支線205系の老朽化に伴う車両置換えのため、はるばる首都圏へ転属する事となった。 |
 |
■205系1000番台(2002年) 南武支線にて永らく活躍した101系の老朽化に伴い、205系に2両編成化改造を施したうえ、転入したのが1000番台。前面形状は基本編成とは異なる新しい形状となる。編成の関係で全てが電動車となるため、加速力が半端ない。当初は2023年にて引退の予定であったが、代替で新潟支社より転属されたE127系の冷房装置が芳しくない事から、現在も活躍中。 |
 |
■209系(南武線:1993年〜2015年) 国鉄より引き継いだ103系の置換えのため登場した車両。南武線には、京浜東北線とともに初期に投入されたが、京浜東北線とは異なり2本が投入されたに留まり、以後は山手線から転入した205系にて103系を置き換えている。その後の京浜東北線からの転入により最盛期には4編成となったが、南武線の車両統一のため2015年にて撤退した。 |
 |
■205系(南武線:1989年〜2015年) 101系の老朽化に伴い投入された車両。南武線初のステンレス車両で、ストライプカラーが注目されたが、公募の結果、沿線中学生による「推しのサッカーチームのユニフォームカラー」であった色(おそらく西ドイツ)を色味アレンジして採用した。ただ何故か現在では「歴代の車体の色」という理由が広まっている。南武線では2015年まで活躍した。 |
 |
■101系(南武線:1969年〜1991年) 大手私鉄では戦後すぐに、走行時の騒音低減を実現したカルダン駆動など、車両の高性能化がすすめられたが、一歩出遅れていた国鉄においての、初の「新性能車」である。南武線には1969年に投入が開始され、9年かけて旧型車を淘汰した。老朽化に伴い本線からは1991年に姿を消したが、2両編成が組めたため支線では2003年まで活躍した。 |
 |
■E131系1000番台(2023年) 横浜の鶴見駅から京浜工業地帯を目指す鶴見線の車両。205系の老朽化に伴い投入された。車両デザインは、海をイメージした青と路線カラーの黄色のストライプとし、前面には歴代鶴見線車両の車両カラーをイメージした茶色と黄色の水玉模様を配した。鶴見線の車体限界の都合上、車体幅が既存E131系より狭い。また前面形状は貫通構造に見えるが非貫通構造。 |
 |
■205系1100番台(2004年〜2024年) 103系の老朽化に伴い、山手線205系の中間車を先頭車化改造のうえ投入した車両。鶴見線初のステンレス車両で、ストライプはラインカラーの黄色に加えて、海をイメージした水色が追加された。老朽化のため2024年をもって引退した。 |
 |
■103系(鶴見線:1990年〜2006年) 101系の老朽化に伴う置き換えとして投入された車両。当初は本線および海芝浦支線での運用で、大川支線は、武蔵白石駅構内の急カーブ上に大川行ホームが立地していたため、入線できなかったがクモハ12形の引退に伴う線形改良および武蔵白石駅大川支線ホームの廃止により(分岐駅は安善駅へ変更)全線への乗り入れが実現した。2006年に引退した。 |
 |
■クモハ12形(1927年〜1996年) 戦前に製造された17m通勤型電車のうち、このクモハ12形は単行での運転ができるよう両運転台とされた。この構造と短い車体長が幸いし、鶴見線の本線では1972年までに72系に置き換えられたのに対し、20m級大型車の入線が不可能な大川支線用として奇跡的に平成の世まで活躍した。だが寄る年波には勝てず1996年に引退した。 |
 |
■E233系6000番台(2014年) 東京・八王子から町田、長津田を経由し神奈川県の東神奈川に至る横浜線の車両。205系の老朽化に伴い投入された。横浜線は一部列車が京浜東北線・根岸線に乗り入れるため、誤乗防止の観点から車内配色が青系の京浜東北線用E233系1000番台に対し、当番台は緑系となっている。 |
 |
■E231系3000番台(2018年) 八王子から群馬県の高崎までを結ぶ八高線は、うち八王子〜高麗川間が1996年に電化され、高麗川から川越線に乗り入れている。その区間の電化開業時より活躍した車両の老朽化に伴い、総武線からE231系を転用され改造を施したのが3000番台である。短編成化、寒冷地用ドア開閉ボタン、ワンマン運転用途とした乗降確認カメラを備える。4両編成6本が所属。 |
 |
■209系3500番台(2018年) E231系3000番台と同様の理由により、総武線から209系500番台を転用、改造された車両。4両編成5本が所属。 |
 |
■E131系500番台(2021年) 神奈川県の茅ケ崎より海老名を経由して橋本に至る、相模線の車両。205系500番台の老朽化に伴い登場した。E131系は房総地区や栃木地区など、線区毎の事情に柔軟に対応できる構造としているが、500番台はその相模線バージョン。ストライプは湘南の海をイメージした濃淡のブルーとし、前面はダイナミックな波の水飛沫を表した水玉模様を採用している。 |
 |
■205系500番台(1991年〜2022年) 相模線用車両。気動車だった相模線の電化開業と同時に投入された車両で、他線区に投入の車両とは前面形状が大幅に変更されている。単線区間を走る路線ゆえ、列車交換など駅での停車時間が長くなるため、室内保温の目的で乗降扉は半自動化され、乗客がドアスイッチにより開閉を行う構造となる。老朽化により2022年で引退した。 |
 |
■205系3100番台(2002年) 東北最大の都市である宮城県の仙台と、太平洋沿いの港町である石巻を結ぶ、仙石線の車両。103系の老朽化に伴い投入された。山手線などから205系を転属し、寒冷地対策、乗降扉の半自動化改造を施し4両編成とした。老朽化に伴い2026年春までに引退が予定される。 |
 |
■205系3100番台「2WAYシート編成」(2002年) 第2・3・4・5・8編成は、ロングシート/クロスシートへ変換可能な「2WAYシート」を装備する。また当該編成はストライプを、赤(石巻市の花であるツツジ)、オレンジ(松島の朝日と夕日、扇谷の紅葉)、紫(塩釜港に水揚げされる魚)、緑(杜の都・仙台)を各々の車両に配す。なお現在は仙石東北ライン開業に伴う快速廃止のため、ロングシートに固定される。 |
 |
■205系3100番台「マンガッタンライナー」(2003年) 第8編成は、宮城県出身の漫画家・石ノ森章太郎氏の作品キャラを各車両にラッピングされ「マンガッタンライナー」として登場した。人気を博したため後には第2編成にもラッピングが施された。なお第8編成は老朽化に伴い2025年春に引退しており現在は第2編成のみの活躍となる。 |
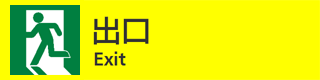 |
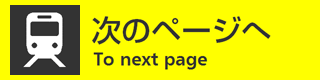 |