 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
■キハ5020形(2019年) 常総線用の最新鋭車両。単線区間である下館〜水海道間を含む全線で使用される。キハ313+314の引退に伴う代替として製造された。外観はキハ5010形を踏襲しつつ、前照灯は上部に配置変更され、かつLEDが採用された。また側面の筑波山をイメージしたエンブレムはカラーが紅梅とされた。 |
 |
■キハ5010形(2017年) 常総線用車両。単線区間である下館〜水海道間を含む全線で使用される。外観はホワイトに、鬼怒川・小貝川をイメージしたブルーと豊かな大地に波打つ稲穂のイエローの新塗装となった。ディーゼルエンジンは軽量化され、また車内の照明にはLEDが用いられるなど、環境負荷のさらなる軽減が図られた。 |
 |
■キハ5000形(2009年) 常総線用車両。単線区間である下館〜水海道間を含む全線で使用される。キハ2400形をベースとしてディーゼルエンジンを環境対応の最新型に変更した。また乗降扉の窓が大型化されている。塗装は従来の京成グループ観光バスに類似した塗装から、沿線を流れる鬼怒川や小貝川をイメージしたブルーと、常総線をイメージした赤の新塗装へと変更された。なお2013年導入の2次車ではスカート(排障器)が大型化された。※画像は2次車。 |
  |
■キハ2400形(2004年) 常総線用車両。単線区間である下館〜水海道間を含む全線で使用される。外観はキハ2200形に酷似するが、キハ2300形で採用した電気指令式ブレーキを、この車両でも採用した。また乗降扉の鴨居部にはLED電光表示機が設置された。なお現在はキハ5000形に準じた新塗装へと変更された。またキハ2401号とキハ2402号には、2022年に創立100周年を迎えるにあたりプレイベントとして、前年に1960年代の旧塗装が施された。 |
 |
□キハ2300形(2000年) 常総線用車両。複線区間である水海道〜取手間で使用される。外観はキハ2100形に酷似するが、キハ2100形では旧型車との連結を考慮して空気式ブレーキとなっているのに対し、この車両では応答性の高い電気指令式ブレーキを採用した。これにより安全性の向上と維持コストの低減が実現した。現在は朝夕を中心に運用される。※画像は旧塗装車(現存せず) |
 |
■キハ2200形(1997年) 常総線用車両。単線区間である下館〜水海道間を含む全線で使用される。新世代気動車であるキハ2100形をベースとしているが単線区間での利用実態に合わせて1両編成となる。また単線区間の無人駅での、運転士による運賃授受を円滑に行うため、運転室直後の乗降扉は片開きとなり、車体中央の両開き扉とは異なる扉が混在する珍しい構造となる。 |
 |
□キハ2100形(1994年) 常総線用車両。複線区間である水海道〜取手間で使用される。従来の気動車のイメージを払拭すべく、都会の通勤電車の雰囲気を取り入れた車両で、室内の配色は親会社の京成3700形に類似する。ディーゼルエンジンは小型・高性能のエンジンを使用、電車に近い加速を誇る。現在は朝夕を中心に運用される。 |
 |
□キハ0形(1982年) 常総線用車両。複線区間である水海道〜取手間で使用される。旧国鉄気動車であるキハ20系を譲受し、通勤輸送に対応させるため車体を新たに製造した。キハ310形と同様の車体ながら、導入当初より前面に方向幕が設置され、また貫通幌の設置により常総線車両では初めて車両間の通り抜けが可能となった。現在は朝のラッシュ時に運用される。 |
 |
■キハ2000形(1997年) 竜ヶ崎線用車両。常総線用2100形をベースに両運転台とした車両であるが、常総線車両と違い全ての扉が両開きとなる。竜ヶ崎線車両は、各駅のホームが全て竜ヶ崎方向右側に配置されているため運転士負担軽減目的で竜ヶ崎側運転台が右側配置となり、前後で運転台位置が異なる、珍しい車両となる。 |
 |
■キハ2000形「まいりゅう号」(2014年) 竜ヶ崎線用車両である2000形のうち2002号は、龍ケ崎市の市制施行60周年を記念して、龍ケ崎市のマスコットキャラクターである「まいりゅう」のラッピングが施された。「まいりゅう号」として毎月第2・第4日曜日に終日運行のほか、平日にも不定期運行される。 |
 |
■キハ532形(1981年) 竜ヶ崎線用車両。国鉄キハ20系の走行機器を流用し、キハ310形と同様の車体を新製し登場した車両。竜ヶ崎線は1971年に日本で初めてワンマン化された鉄道路線で、かつ竜ヶ崎線は各駅のホームが全て竜ヶ崎方向右側に配置される。そのため竜ヶ崎線用車両は運転士負担軽減目的で竜ヶ崎側運転台が右側配置となり、前後で運転台位置が異なる。 |
  |
□キハ310形(1977年〜2023年) 常総線用車両。複線区間である水海道〜取手間で使用された。旧国鉄気動車であるキハ10系を譲受し、通勤輸送に対応させるため車体を新たに製造した。2両編成の車両であるが車両間に貫通幌は設置されておらず車両間の通り抜けはできない。登場時はキハ532形に類似した前面形状であったが、更新工事によりキハ0形に酷似する前面となった。キハ313+314は関鉄の旧塗装が施されていた。老朽化のため2023年をもって引退した。 |
  |
■キハ300形・350形(1986年〜2011年) 常総線用車両。旧国鉄の通勤型気動車であるキハ30系とキハ35系を購入の上、改造を施した車両で、運転台が前後両方にある両運転台車が300形、片運転台車が350形。301号は、筑波鉄道(現在廃止)が国鉄から購入した車両を同鉄道の廃止に伴い関鉄が譲受した経緯がある。老朽化のため2011年をもって引退した。 |
 |
■キハ100形(1997年〜2017年) 常総線用車両。単線区間である下館〜水海道間で使用された。単線区間のワンマン運転化の際にキハ300形をワンマン運転仕様に改造して登場した。キハ101は国鉄気動車をイメージした朱色に、キハ102はクリーム色と青の復刻旧塗装となった。2017年をもって引退した。 |
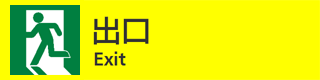 |
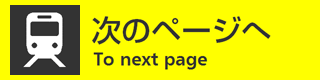 |