 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
■2100形(1998年) 開業100周年を記念して登場した快特用車両。座席は転換クロスシート(車端部はボックスシート)で常に進行方向を向くよう、始発駅で一括転換が可能。座席自体も海外製の瑠璃色の座席で、特別料金不要特急とは思えない豪華さ。VVVFインバータは起動時に「ドレミファ〜♪」と特異な音を発するのが特徴であったが、現在は機器更新により通常の走行音となる。 |
 |
■1000形(2代目・2002年) 老朽化した旧1000形を置換えるべく登場した車両。旧1000形とは在籍時期が重複していたため「新1000形」とも呼ばれる。車内の座席は、ロングシートが基本であるが車端部にはボックスシートを備える。制御装置はVVVFインバータで、初期は「ドレミファ〜♪」と特異な音を発するタイプであった。現在は機器更新により通常の走行音となる。 |
 |
■1000形ステンレス車(2007年) 京急の主力車両である1000形は2007年製造の6次車より、今まで頑なに「赤い電車」を貫き通した京急にとって初のステンレス製車体となった。ただしイメージを踏襲すべく、側面には広幅の赤いフィルムが貼付された。また踏切事故対策として運転台は高運転台化され、また前面強度も1.5倍の強度とした。車内は全てロングシートとなっている。 |
 |
■1000形(1800番台・2016年) 1000形は、15次車のうち一部編成で、朝ラッシュ時の増結用途として、また全般検査などで浅草線直通運用の8両編成が不足した際に2編成を連結して8両編成とできるよう、前面貫通扉を中央に配置した編成が登場している。15次車からは側面のカラーフイルム貼付が、塗装編成に極力合わせたデザインとなっている。 |
 |
■1000形(1890番台・2021年) 1000形のうち20次車は、座席指定列車やイベント列車対応のため京急初となるデュアルシートを初採用した。中間車にはトイレを設置した。車体は1800番台をベースとしつつ、総合車両製作所の車体製造工法「Sustina」を採用、平滑な車体となった。「LeCiel」の愛称を持つ。2022年の鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞車両。 |
 |
■600形(3代目・1994年) 旧1000形の置換えを目的として登場した車両。居住性の向上を図るべく、通勤型車両、しかも地下鉄直通対応車両としては非常に珍しい、全席クロスシートとした。前面形状は3次元曲面の優雅な形状。登場当時は前面窓下はグレー塗装であったが、視認性向上のためアイボリーとされた。なお現在は更新工事により車端部以外はロングシート化されている。 |
 |
■600形「京急ブルースカイトレイン」(2005年) 600形のうち606編成は、2005年3月に更新工事を施された際に、車体色をブルーに変更、広告貸切列車「京急ブルースカイトレイン」として登場した。また同年6月には2100形2157編成にも同様の塗装が施された。特殊塗装であるが運用は他編成と共通運用とされている。なお2100形のみ、京急ホームページにて運用を公開している。 |
 |
■1500形(1985年) 旧1000形に代わる、地下鉄浅草線乗入れ用車両として登場。外観は2000形譲りのデザインとなる。また現在の地下鉄乗入れ車両の中では全車がロングシートであるなど、地味な印象の車両である。1990年増備車からは、制御装置が京急初のVVVFインバータ制御となり、前面にはスカート(排障板)が設けられた。 |
 |
■2000形(1982年〜2018年) 旧600形の老朽化に伴い、優等車両として遜色ない仕様を採用し登場した車両で、京急に新風を吹き込んだ。前面形状はスピード感あふれる外観となる。両開き扉や角型2灯の前照灯など京急初の新機軸を数多く採用したこの車両は、鉄道友の会「ブルーリボン賞」を受賞。晩年は通勤型へと格差げされ3扉化された。老朽化のため2018年をもって引退した。 |
 |
■800形(1978年〜2019年) 普通列車の速度向上を目的として登場した車両。乗降扉は4扉となる。また登場当初は、赤地に窓周りが白という新塗装で登場した。ただしこの塗装を後に「優等列車用」と制定されたため2000形に譲り、800形は従来の白帯塗装に戻された。鉄道友の会「ローレル賞」受賞。正面の塗り分けから「ダルマ」と呼ばれた。2019年をもって引退した。 |
 |
■1000形(初代・1959年〜2010年) 都営地下鉄浅草線の泉岳寺延伸に伴う直通運転の開始を事前に控え乗入れ用車両として登場した。当初は、前面に貫通扉のない非貫通構造であったが、地下鉄直通規格に合わせて前面に貫通扉を設置した。19年間で356両が製造され、京急の代表車両として親しまれたが、老朽化には勝てず2010年をもって引退した。現在は一部車両が高松琴平電気鉄道に譲渡される。 |
 |
■700形(1967年〜2005年) ラッシュ時の乗降時間短縮のため京急初の4扉車で登場した車両。製造コスト削減のため、一部に電動装置を積まない車両を連結したが、加速の遅い車両となってしまい、本来の普通列車運用よりも加減速の少ない優等列車に使用されるという、車体と性能が比例しない車両となってしまった。晩年は専ら大師線を住み家としていたが、2005年をもって引退した。 |
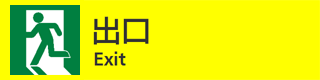 |
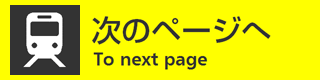 |