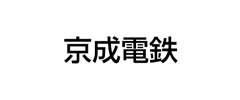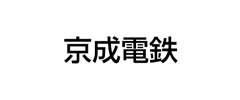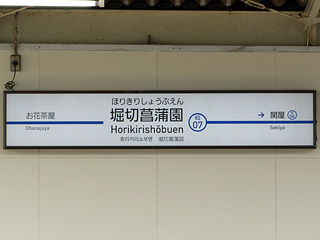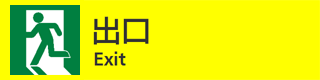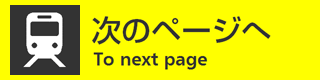|
 |
■AE形(2010年)
上野と成田空港を結ぶスカイライナーに使用される車両。2010年に開業した成田スカイアクセスでの160キロ運転に対応。山本寛斎氏によるデザインは「風」と「凛」をコンセプトとし、和の伝統色である藍、スピード感を強調した白の塗装となる。鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞、また「グッドデザイン賞」も受賞している。 |
 |
■3200形(2代目・2025年)
3500形の老朽化に伴い登場した車両。3100形に続き、京成グループ標準車両として設計された車両であるが、輸送需要の変化に応じたフレキシブルな運用が可能なよう、組成組み換え可能な車両となる。座席は一般席を青基調、優先席を赤基調とし、ソメイヨシノ・なのはなをモチーフとした京成線沿線地域を想起させるデザインとなる。
|
 |
■3100形(2代目・2019年)
成田スカイアクセス線の増発と3600形の老朽化に伴い登場した車両。外観は、成田スカイアクセス線の案内カラーであるオレンジを基調としたデザインとし、戸袋部には沿線名所のイラストが入る。車内は座席の一部を折りたたみ式とし、空港利用客の大型荷物に対応した。制御装置はSiC−VVVFインバータを搭載し3000形より15%の消費電力削減を実現した。
|
 |
■3000形(2代目・2003年)
「赤電」こと初代3000系列を置き換えるべく登場した車両。製造工程短縮のため鋼体は、日本車輌が開発した、ステンレスをブロック状に組み合わせる工法を採用。さらにドアチャイムの初採用や優先席付近のつり革を低くするなど、乗客に配慮した仕様とした。なお、この車両は、京成グループ標準車両と位置づけられる。
|
 |
■3700形(1991年)
初代3000系列のうち、非冷房車の置き換えと北総線乗入れ用として登場した車両。スカイライナーの塗色である赤と青のストライプを採用、従来の京成のイメージを払拭した。また京成の新造通勤車両では初めてVVVFインバータ制御を搭載。特急から各停までと幅広く活躍する。なお、北総7300形はこの3700形と同一思想に基づく共通設計車両である。
|
 |
■3700形(6次車〜・2000年)
京成の主力車である3700形は2000年製造の6次車から仕様変更が行われた。外観はヘッドライトが上部へ移設され、逆に優等列車表示灯は下部に移設し、細長い形状の尾灯と共に並べられた。パンタグラフはシングルアーム式となり、室内の座席仕切板は大型タイプとなる。6次車と7次車は6両編成で製造され、千葉線でも活躍する。
|
 |
■3400形(1993年)
初代スカイライナーAE車は、後継のAE100形に役割を譲るも、製造からまだ20年前後であるため走行装置や空調機器を再利用、車体のみ新製して通勤車へと変身。この車両を3400形とした。車内設備は3700形と同等。なおこの頃、京成では新塗装を検討していたが、3400形で採用のグレー塗装が広まる結果となった。
|

 |
■3600形(1982年)
「青電」と呼ばれる旧性能車の置換えを目的として導入された車両。京成では初の、外板のほかに骨組や台枠にもステンレスを採用したオールステンレス車体となり、車体の劣化低減を実現。電動装置の出力増加により先頭車両は電動装置をなくしコスト削減に寄与したが、この仕様が京急乗入れ規定に抵触する事から、京急への乗入れには対応していない。老朽化に伴い廃車が進み、風前の灯火となる。
|
 |
■3500形(1972年)
京成初のステンレス車両。外板の塗装が不要となり塗装コスト低減を実現。また京成通勤車両では初の冷房搭載車で登場するや否や人気を博した。1996年より3700形に準じたリニューアル工事が施工され、新車と遜色ない雰囲気となった。なお、リニューアル工事が施されなかった編成は2017年までに廃車となっている(詳細は「懐かしの車両」欄)
|
|
 |
■80000形(2019年)
京成松戸線用車両。8000形の老朽化に伴い登場した。「受け継ぐ伝統と新たな価値の創造」をコンセプトに開発された。外観デザインはやわらかさを醸し出すため、丸みを帯びた形状となり、新たに上部にもピンクのラインを配した。車内には防犯カメラを設置、また液晶式の案内表示器やプラズマクラスター発生装置の搭載など、車内環境の改善を図った。 |

 |
■N800形(2005年)
京成松戸線用車両。京成千葉線への直通運転開始と800形の置換えを目的に導入された。800形以降、京成とは異なる独自設計の車両を導入し続けてきた新京成(当時)において、34年ぶりに共通設計車両が登場した。登場時は沿線の4自治体を表す4本のマルーンのストライプを施したが、ピンク塗装を経て、今後は京成標準色への変更が予定される。
※下段は登場時。 |
 |
■8900形(1993年)
京成松戸線用車両。新京成(当時)初のステンレス製車両で、また純電気停止ブレーキや、シングルアームパンタグラフは、機関車を除く電車では日本初の搭載となる。車体色は社内公募によりブルーとピンクのストライプとなるが、その後ピンクがルビーレッドへ変更、さらに現在はジェントルピンク基調の塗装となる。
|

 |
■8800形(1986年)
京成松戸線用車両。VVVFインバータを、量産を目的とした新造車両としては日本で初めて搭載した車両(軌道線や試作車を除く)登場当初はアイボリー地に茶帯であったが、千葉線への直通運転を機に、直通対応とした編成がマルーン帯へと変更され、さらにジェントルピンク基調の塗装を経て、今後は京成標準職へと変更される予定。
※下段は登場時塗装。
|
 |
 |
■AE100形(1990年〜2016年)
1991年の空港直下乗入れを控え、2代目スカイライナーとして登場した車両。当初は地下鉄浅草線への直通が計画されたため、特急車ながら前面に非常用貫通扉を装備する。前照灯はスポーツカーを思わせる格納式。2010年、主役の座をAE形に譲り、新設の「シティライナー」に充当されるが、シティライナーの定期運用廃止に伴い、2016年をもって引退した。
|
 |
■AE車(1972年〜1993年)
成田空港の開港に併せて製造された、日本初の空港連絡特急車。鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞車両。室内は空港利用者に配慮して荷物室を設ける。登場時はクリームとマルーンの塗色であったが、後に画像の塗色へと変更され、これが現在の京成のイメージカラーとなる。AE100形の登場により引退。現在は走行装置を再利用し3400形となる。 |

 |
■3000形・7次車(2010年〜)
3000形のうち成田スカイアクセス線開業に伴い増備された7次車は、成田スカイアクセス線内での高速運転に対応すべく130キロ運転対応とし、室内の乗降扉鴨居部には液晶ディスプレイが設置された。登場時はブルーの外観であったが、2019年からは路線カラーに合わせたオレンジ系への外観となった。現在は成田スカイアクセス線から撤退、ストライプも赤と青へと再変更された。
※下段はオレンジカラー。
|
 |
■3500形(1972年〜)
京成初のステンレス車両である3500形は、登場当時は左記の外観であり、かつストライプも青帯はなく、朱色の帯のみであった。1996年より3700形に準じたリニューアルが行われたが、思いのほか老朽化が進んでいたことからリニューアルは全編成には及ばず、以降は3000形の新造となった。未更新編成は2017年をもって引退した。
|
 |
■3300形(1968年〜2015年)
京成初の高性能車である3000形(初代)の流れを汲む車両。設計コンセプトは3200形を踏襲しながらも、前面や側面には行先方向幕が本格搭載された。1989年より更新工事が行われ、前面が画像の形状となった。京成最後の「赤電」として人気を博したが、老朽化により2015年をもって引退した。
|
 |
■3300形リバイバル塗装・青電(2009年〜2013年)
2009年に創立100周年を迎えた京成の記念行事として、3356編成が青緑の濃淡色の通称「青電」塗装へと変更され登場した。青電は1952年登場の2100形に初めて塗装され、以後、3000形(初代)まで踏襲。1982年に行商専用車であった2200形が廃車されるまで存在した。なお3356編成は老朽化のため2013年に引退した。
|
 |
■3300形リバイバル塗装・赤電(2009年〜2013年)
2009年に創立100周年を迎えた京成は記念行事として、3324編成を、クリーム色とファイアオレンジ、そしてミスティラベンダー帯の通称「赤電」塗装へと変更された。「赤電」塗装は1959年登場の3050形(初代)に初めて塗装され、京成のイメージアップに貢献した。なお3324編成は老朽化のため2013年に引退した。 |
 |
■3300形リバイバル塗装・新赤電(2009年〜2013年)
2009年に創立100周年を迎えた京成は記念行事として、3312編成を、ファイアオレンジとクリーム帯の、通称「新赤電」塗装へと変更し登場させた。「新赤電」塗装は京成の経営悪化に伴うコスト削減により採用された塗装で、登場当時は「会社が赤字だから電車も赤い」と揶揄された。なお3312編成は老朽化のため2013年3月に引退した。 |
 |
■3200形(初代・1964年〜2007年)
3000形(初代)の流れを汲む車両。乗降扉は京成初の両開き扉を採用、それに伴い窓配置も大幅に変更された。登場当初は行先表示幕が搭載されていなかったが、1985年より行われた更新工事により画像の形状となった。最終増備車である3290番台は特急「開運号」用として製造された(詳細は後述)老朽化に伴い2007年をもって引退した。
|
 |
■3200形・3290番台(1967年〜2007年)
最終増備車である3290番台は、特急「開運号」用車両であった1600形の置換えとして登場した。室内はボックスシート、トイレ、車販準備室が設置されたが、AE車登場までの「つなぎ」のため外観は通勤車両そのものであった。AE車登場後はトイレや車販室の撤去、ロングシート化が行われた。晩年は「開運号」復刻運転が行われた。2007年をもって引退した。 |
 |
■3200形・試験塗装車(1991年〜1993年)
評判の悪かった「新赤電」塗装を改めるべく、所属車両の新塗色が検討された。レッドとブルーをストライプ色に採用し、ベース色はグレー・ホワイト・ライトブルー・イエローグリーンの4色が登場し話題となったが、結局は3400形で採用されたグレーがそのまま広まる結果となった。画像は最も短命に終わったライトブルー基調の試験塗色車。
|
 |
■3050形(初代・1959年〜1995年)
都営地下鉄浅草線との直通運転用途として製造された車両。塗装はクリーム色とファイアオレンジ、ミスティラベンダー帯の通称「赤電色」を初採用。明るい塗装は、京成のイメージアップに貢献した。老朽化に伴い1995年をもって引退した。 |
 |
■2100形(1952年〜1988年)
戦後初の本格的な導入車両。登場当初は半鋼製ながら平滑な車体とされ「青電」塗装も当初から施された。1962年以降からは更新工事により車体が全鋼製化された。後年は他の車両と同様にファイアオレンジ基調の「新赤電」塗装とされたが、引退時のさよなら運転の際に「青電」塗装が復活した。老朽化のため1988年をもって引退した。
|
|



 |
■8000形(1978年〜2021年)
新京成(当時)初のオリジナルデザイン車。正面形状から「くぬぎ山の狸」と呼ばれる。登場時の塗色はキャンディピンクとマルーンで、後にアイボリー地に茶帯に変更。そして2006年よりマルーン帯へ、さらに晩年はジェントルピンク機長の塗装へと変更された。後年は更なる省エネとメンテナンスの簡略化を目的としてVVVFインバータ制御化改造が施されたが、老朽化に伴い2021年11月をもって引退した。
|
 |
■800形(1971年〜2010年)
開業当初から京成の中古車両で営業していた新京成(当時)において初の完全自社発注車。もっとも塗装以外は京成3100形と酷似したデザインで登場したため、新車の印象は薄かった。また後の更新で、当初上部にあった前照灯が京成旧3000系列のように下部に移設された他、行先表示幕の設置と貫通扉の固定化が行われた。老朽化のため2010年をもって引退した。 |
|
 |
■千葉急行電鉄・1000形(1992年〜1994年)
小湊鉄道が所有していた千葉〜海士有木(あまありき)間の免許を譲受のうえ設立した千葉急行電鉄の、初代車両。元々は京成が京急からリースしていた1000形を、塗装変更のうえ千葉急行へと貸し出した。しかし元々車齢が高かった事から僅か2年で廃車となった。なお、千葉急行電鉄自体も経営破綻のため会社清算となり、路線は京成が引き継ぎ千原線としている。
|