 |
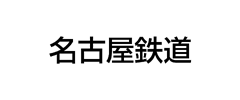 |
 |
 |
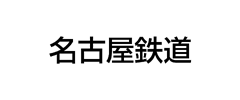 |
 |
| にょほほ電鉄−車両−名古屋鉄道 |
|||
 |
|
||
| 駅名標 名古屋鉄道 |
|||
 |
|
||
  |
|
||
 |
■2000系(2005年) 中部国際空港開港とともに登場した特急車両で「ミュースカイ」の愛称で呼ばれる。空のイメージである青をアクセントとした。曲線区間も高速に走行できるよう車体傾斜装置を初装備。室内には空港特急らしく荷物置場が設置されている。鉄道友の会「ローレル賞」受賞車。また「グッドデザイン賞」も受賞している。 |
 |
■2200系(2005年) 2000系とともに空港アクセス特急として登場した車両。しかし2000系とは違って一般車が併結されており、塗装も従来の名鉄と同様に赤基調となる。また2000系で装備されていた車体傾斜装置は、この車両では搭載されていない。空港輸送が中心であるが通常の特急運用にも充当される。 |
 |
■1000系・1200系(1988年) 名鉄線の東西直通40周年を記念して登場した車両。より高い快適性に応えるべく設計された。先頭車は1階が運転室、2階が展望室となり快適な眺望を実現。当初は全車座席指定であったが、JR東海への対抗措置として1991年に一般車4両を併結、豊橋方2両が座席指定車の1000系、岐阜方4両が一般車の1200系となる。※画像は旧塗装時代。 |
 |
■9500系・9100系(2019年) 所有車両の扉配置の統一化及び6000系の老朽化に伴い登場した車両。車体は3300系を踏襲するが、前面形状は赤色を全面にまとい、前照灯はLED化されシャープな印象となる。4両編成が9500系、2両編成が9100系。なお前面形状は6次車より、連結運転時の常時通り抜けを想定し幌座付きの形状となった。 |
 |
■3300系・3150系(2004年) 本線系統では初のステンレス製車両。名鉄初のステンレス製車両である小牧線用300系をベースとしながら19m中型車・3扉車となっている。シルバー地ながらスカーレット色のストライプで名鉄車両をアピール。4両編成が3300系、2両編成が3150系。 |
 |
■5000系(2008年) 特急列車の運用見直しによって一部が余剰廃車となった1000系の廃車発生品を流用して通勤車両化した車両。車体は3300系と同様のものとなるが、前面形状は流用部品の関係で非貫通構造となる。また前照灯周りの装飾が簡略化されている。 |
 |
■300系(2002年) 都心側ターミナルに接続路線がなく、永らく不便を強いられてきた小牧線の環境改善のために開業した、地下鉄上飯田線との直通運転用に製造された車両。名鉄初のステンレス車体を採用、ストライプは名鉄の赤と上飯田線のピンクをまとう。 |
 |
■3700系・3100系(1997年) 名鉄初のVVVF制御車である3500系のマイナーチェンジ車。性能等は3500系と同一であるが、車体断面が従来のタマゴ形ではなく、側面が垂直となっているのが特徴。4両編成が3700系で2両編成が3100系。 ※手前2両が該当車両の3100系。 |
 |
■3500系(1993年) 名鉄初のVVVF制御車両。運転台のマスコン(ハンドル)もワンハンドルとなるなど新機軸を随所に盛り込んだ車両である。前面に掲げられた「ECB」エンブレムは、電気指令式ブレーキの意味。前面形状は6500系後期車に倣った「金魚鉢」形状。なお登場当初は乗降扉がグレーと赤の塗色であったが、現在は他車両と同様に赤一色となっている。 |
 |
■6500系(1984年) 6000系をベースに制御装置を界磁チョッパ制御とした車両。前面形状は6000系後期車と同様の、いわゆる「鉄仮面」と呼ばれる形状。車体寸法等、以後の名鉄車両の標準となった車両である。 |
 |
■6500系(6次車・1987年) 6500系は1987年登場の6次車からは5700系の前面形状をモチーフとした丸みのある前面形状となった。車内からの眺望を良くするための改良であるが、球面のガラスから「金魚鉢」なる称号が与えられている。 |
 |
■6000系(1976年) 従来の名鉄車両の標準であった2扉・クロスシート車両では混雑時に対応しきれなくなった事から、他都市と同様の3扉車で製造された車両。ただし座席は集団離反式のクロスシートとなり、名鉄のこだわりが伺える。鉄道友の会「ブルーリボン賞」を、通勤車両では初めて受賞した。なお9次車以降は6500系初期車と同様の前面形状となる。 |
 |
■1030系・1230系(1993年〜2019年) 1000系の運用拡大による車両不足に伴い廃車された7500系の走行装置を流用して車体のみ1000系と同様の車体で製造された車両。座席指定車が1030系、一般車が1230系。外観は殆ど変わらないが、全車電動車である事とパンタグラフの位置が異なる。また台車や制御装置は種車を踏襲する。老朽化に伴い2019年をもって引退した。 |
 |
■7000系(1961年〜2009年) 自動車王国である名古屋においてインパクトを与えるべく開発された車両。何と言っても特徴的なのは、イタリア特急を思わせる前面展望室で日本初の試み。また万一の衝突事故にも耐えうるよう油圧ダンパも装備された。鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞車。老朽化により、惜しまれつつ2009年をもって引退した。 |
 |
■5700系・5300系(1986年〜2019年) SR車と呼ばれる初期の優等列車用車両の老朽化に伴い製造された急行用車両。パノラマカー・7000系の影響が随所に現れており快適性の高い車両である。なお5700系は完全新造車両であるが5300系は廃車となった5000系の走行装置を流用した車両となる。老朽化に伴い2019年年末までに引退した。 |
 |
■1380系(2003年〜2015年) 1993年に登場した1030系・1230系のうち1134編成は、2002年に踏切事故に遭い豊橋方先頭車両は大破した。しかし岐阜方4両は破損を免れ、この4両に一般車化改造を施したのが1380系。その様な経緯ゆえ1編成のみの特異な存在であった。また車内は特急車時代のままであった。2015年をもって引退した。 |
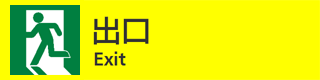 |
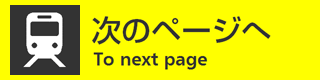 |