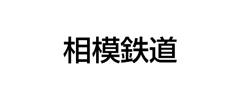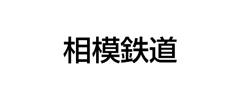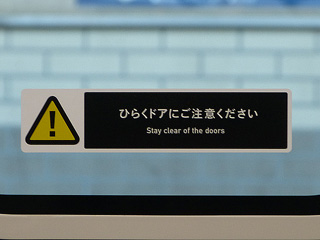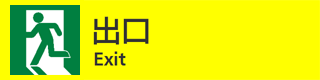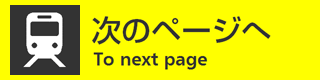|
 |
■12000系(2019年)
相鉄の最新鋭車両。2019年に開始されたJR埼京線との直通運転用途として製造された。外観は東日本旅客鉄道E235系に準じた構造としつつも、ネイビーブルーの塗色や「獅子口」をイメージした特色ある前面形状などインパクトのある外観となる。車内は20000系と共通点の多いグレー基調の内装となる。 |
 |
■20000系(2018年)
東急線との直通運転用途として製造された車両。8000系以来の日立製作所製で、外観は同社開発の車体製造技術「A−Train」をベースとするも、ネイビーブルーの塗色や外国車を思わせる前面形状などインパクトのある外観となる。車内はグレーを基調としたスタイリッシュなデザインで照明は日中と夜で色調が変化する調色LED照明となる。
|
 |
■21000系(2021年)
20000系の8両編成版として製造された車両。東急東横線への直通を考慮した20000系とは異なり、目黒線直通を考慮されているため、車椅子スペースや非常用ドアコックの位置が直通先に合わせられている。2021年に営業運転を開始、2023年には東急線への直通運転を果たした。
|
 |
■11000系(2009年)
5000系や7000系の置換えを目的として登場した。東日本旅客鉄道E233系をベースに製造されている。また車内の乗降扉鴨居部にはLCDモニターが設置されるなど鋼体以外の類似点も多い。10000系と同様に、一部編成はJR新津車両製作所(現・総合車両製作所)で製造された。
|

 |
■10000系(2002年)
2100系、6000系の置換えを目的として登場した車両。製造コスト削減のため、東日本旅客鉄道E231系をベースに製造され低コストでの高性能化を実現。一部編成はJR新津車両製作所(現総合車両製作所)で製造された。反面、相鉄伝統の直角カルダン駆動やパワーウィンドウ(自動開閉窓)等は、この車両では採用されていない。登場当時はグリーン系のストライプであったが、新CI導入に伴い現在は画像の塗装となる。また10701編成はヨコハマネイビーブルー塗装化されている。
|
 |
■9000系(1993年)
6000系の老朽化に伴い登場した車両。従来、相鉄の車両は、例外を除いて日立製作所で製造されていたが、車両更新を早急に進めるため東急車輛(現・総合車両製作所)によって製造された。2017年に創立100周年を迎えた相鉄では記念事業の一環として、塗装を横浜の海に見立てた「ヨコハマネイビーブルー」に変更した。
|

 |
■8000系(1990年)
旧型車である6000系置換えのために登場した車両。「21世紀になっても通用する車両」をコンセプトに製造され、従来の相鉄車にはない大胆な前面デザインで登場した。新7000系の一部で採用されたVVVFインバータ制御を本格的に採用する。また編成のうち2両の車内にはボックスシートを設置。相鉄を代表する車両として急行や快速を中心に活躍する。新CI導入に伴い新塗装化が完了したが、8709編成はヨコハマネイビーブルー塗装化された。また一部では廃車が発生している。
※矢印を画像にかざすと旧塗装車の画像に。
|
 |

 |
■9000系(1993年)
現在はヨコハマネイビーブルー化された9000系は、登場当時はライトグレー地に赤いストライプの塗装であった。2007年、相鉄グループの新CI導入に伴いブルーとオレンジのグループカラーへの変更が行われた。しかし「相鉄デザインブランドアッププロジェクト」発足に伴い、この新塗装も2019年をもって消滅している。
|
 |
■7000系(1975年〜2019年)
相鉄の新造車両では初のアルミ製車両。外観は5000系等のアルミ更新車両をベースとするが、前照灯の位置が両端に寄るなど細部に違いが見られる。側面ストライプは車体最上部と最下部に配されているが、これはアルミ外板の結合部を隠すため。老朽化に伴い2019年をもって引退した。
|
 |
■新7000系(1986年〜2020年)
7000系は、1986年製造車両からは大幅な仕様の変更が生じた。前面形状は前面窓周りを黒色処理とし、前照灯と尾灯が一体化されスッキリした外観となった。またストライプの貼付方法もアルミ板からステッカーへと変更された。最終編成では一部座席がボックスシートへと変更された。老朽化のため2020年をもって引退した。
|
 |
■5000系(1955年〜2009年)
相鉄初の高性能車両。登場当時の車体は張殻構造というタマゴ形断面の車体であったが、車体更新の際に20m級アルミ車体に載せ替え5100系へと改番、さらにVVVFインバータ制御化改造の際に再び5000系となった。老朽化に伴い一旦は運用を離脱したが、踏切事故による車両不足から急遽1編成が復帰した。2009年をもって引退した。 |