 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
■10000形(2008年) グリーンライン用車両。開業時より活躍する車両である。横浜市営初のリニアモーター車両で、開業の実に2年前より導入され、走行試験が行われた。当初は乗降扉脇にブルーのアクセントが配されていたが、直前に路線名がグリーンラインとなったため現在はこの部分はグリーンのアクセントとなる。 |
 |
■10000形(2次車・2014年) グリーンライン用車両。列車増発に伴い2編成が増備された。従来車からの仕様変更は、尾灯の形状変更や行先表示機のフルカラー化また室内にはLED照明が採用された。なお、画像の第16編成はグリーンライン開業10周年の際に、横浜市電を模したラッピングが施されていた。 ※現在はラッピングが剥がされています。 |
 |
■4000形(2022年) ブルーライン用車両。3000A形の老朽化に伴う代替用として登場した。外観は「海辺の先進的な都会感」をコンセプトに、凛とした佇まいとスピード感を感じさせるデザインとした。車体は川崎車両による次世代車両製造技術「efACE」を採用。機能面ではバリアフリーや快適性の向上に加え、防犯カメラの導入など安全性も向上した。 |
 |
■3000形・1次車(1992年) ブルーライン用車両。新横浜〜あざみ野間の延伸開業に伴い登場した。塗装は従来の青い縦縞ではなく、横ストライプとなった。また乗降扉の幅は1.5mワイドドアを採用している。先頭車両の運転室寄りにはボックスシートを設置。前面形状は強化プラスチックの額縁を配した丸みのあるデザイン。老朽化に伴い廃車が進む。 |
 |
■3000形・2次車(1999年) ブルーライン用車両。戸塚〜湘南台間の延伸開業に伴い登場した。前面形状は、丸みのある1次車に対してステンレス鋼のみの直線的なデザインへと変更された。また制御装置や側面のブルー帯にも変更が加えられた。1次車との区別から3000N形とも呼ばれる。「N」とはNewの意味。 |
 |
■3000形・3次車(2004年) ブルーライン用車両。1000形の老朽化に伴い登場した。1・2次車から再び仕様変更され、鋼体は凹凸の無い平滑な外板となり、前面ガラスは下部が丸みを帯びている。従来車との区別から3000R形とも呼ばれる。「R」とはRe‐place(置換える)の意味で、文字どおり旧型車を置換えるために登場した。 |
 |
■3000形・4次車(2005年) ブルーライン用車両。引退した2000形の走行装置を再利用し、新製車体に換装して登場、コスト削減とサービス向上を両立した。車体前面はライトブルーのアクセントを施した。従来車との区別から3000S形とも呼ばれる。「S」とはSatisfaction(満足)の意味で、2000形を満足度の高い設備へと更新する事から名づけられた。 |
 |
■3000形・5次車(2017年) ブルーライン用車両。3000形1次車の老朽化に伴い登場した。各側扉の横には、ヨットの帆をイメージしたグラデーションを施し「ヨコハマを象徴する海を連想させるデザイン」を表した。従来車との区別から3000V形とも呼ばれる。「V」とはローマ数字の「5」を表し、文字どおり5次車である事から名づけられた。 |
 |
■2000形(1984年〜2006年) 横浜〜新横浜間の延伸開業に伴い製造された車両。車体は鋼体全般をステンレスとしたオールステンレス車体となる。逸話として、同時期に製造されていた国鉄205系の視察として車両工場を訪れていた国鉄関係者が、偶然隣にいたこの車両の側面窓を気に入り、以後の205系の窓設計を変更させたという話がある。2006年をもって引退した。 |
 |
■1000形(1972年〜2006年) 横浜市営地下鉄の開業に伴い登場した車両で外板のみをステンレスとしたセミステンレス車体となっている。乗降扉部に青のラインを縦方向に塗装するなど、当時としては斬新なデザインを採用。また登場当時は冷房を搭載していなかったが、後の更新で追加された。老朽化のため2006年をもって引退した。 |
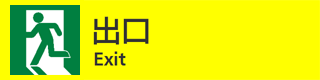 |
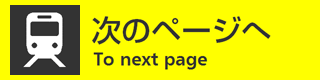 |